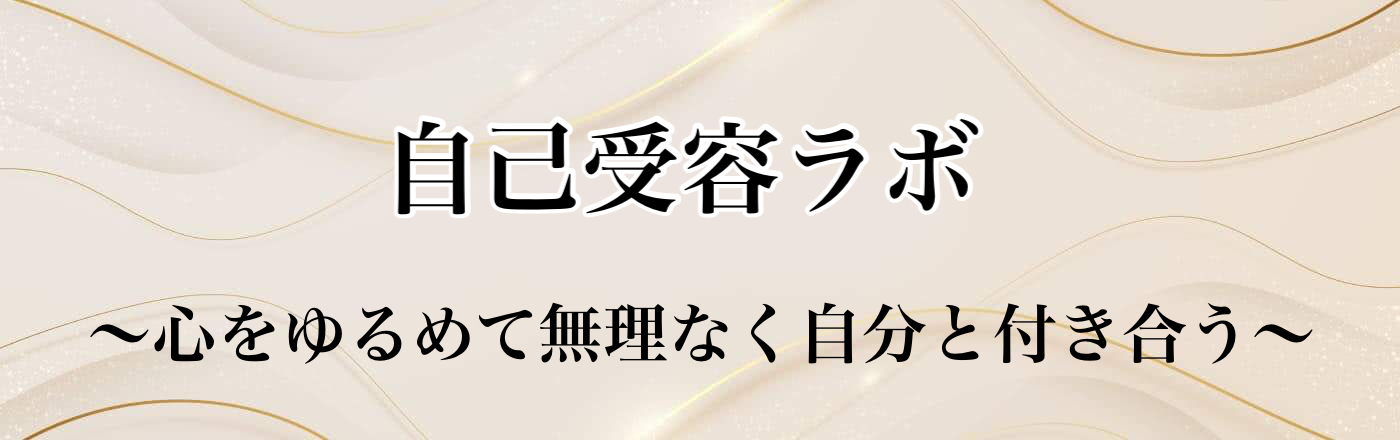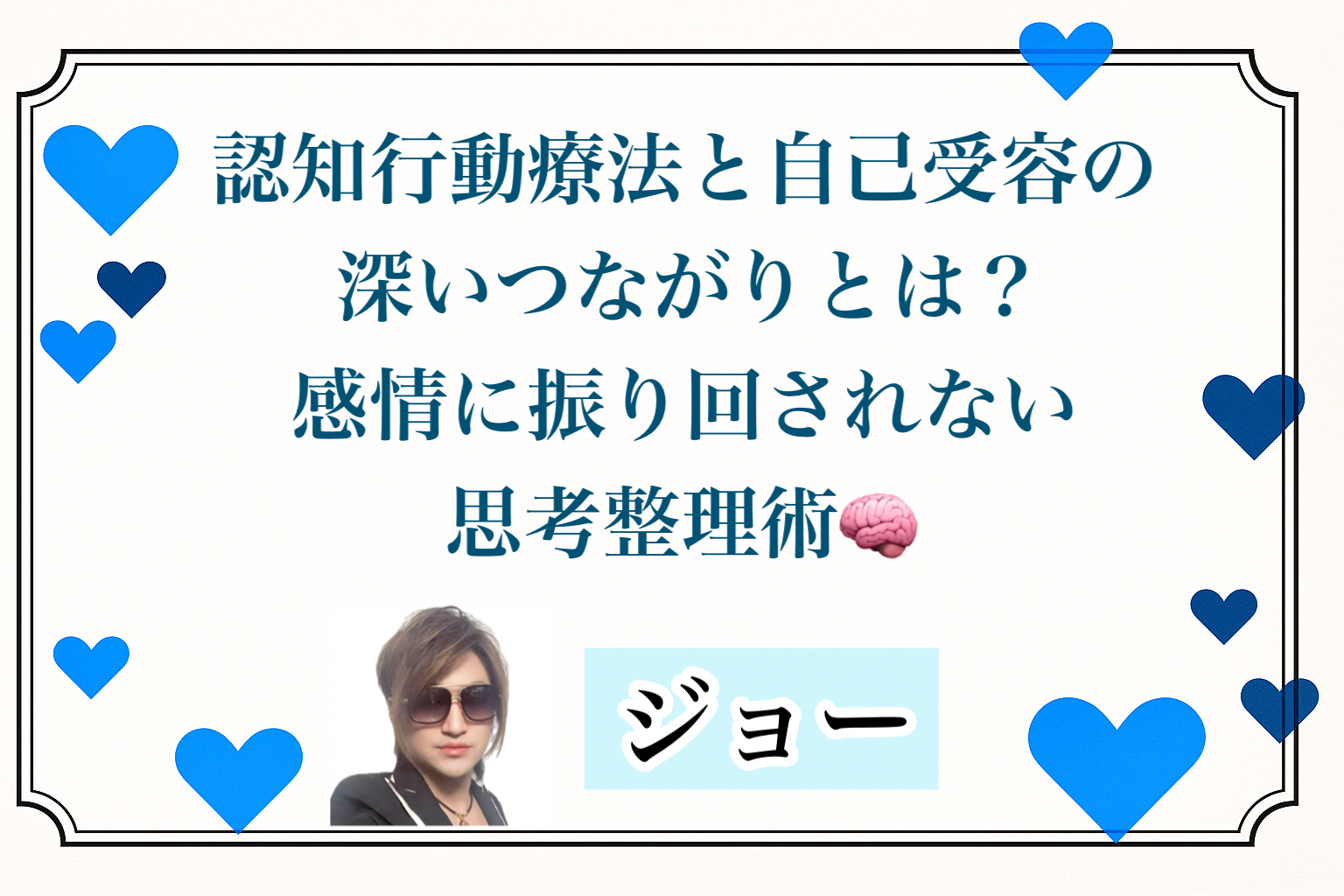自己受容って、言葉では聞いたことがあるけれど「どうやったらできるの?」って悩む人は多いです☺️
「自分を受け入れましょう」なんて聞いても、正直それができたら苦労しないわ…と思いますよね。
実際に自己受容ができないとき、人は“自分自身との関係”において苦しんでいます。
たとえば、
・落ち込んだ自分に「こんなんじゃダメ」と言ってしまう
・うまくいかないと「自分には価値がない」と感じてしまう
・誰かに否定されただけで、自分を丸ごと否定してしまう
こういうふうに、「ある感情=悪いもの」「できない=価値がない」と結びつけてしまうんです。
つまり、感情や思考に振り回されて、自分を客観的に見られなくなっている状態が、自己受容の難しさの正体です🌀
認知行動療法の基本と自己受容との接点
そこで登場するのが、**認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)**です🧠
この療法は、「考え方と思考のクセに気づいて、より生きやすい方向に整える」というアプローチが特徴です。
でも実は、認知行動療法の本質って「考えを変えること」ではなく、
まず“気づくこと”から始まるんですね。
たとえば、
・イライラしてるとき、自分の中に「どうせ分かってもらえない」という思考がある
・不安が強いとき、心の中で「また失敗するに決まってる」と繰り返してる
こうした“自動的に出てくる思考”を、ただそのまま言葉にして見つめる。
それが認知行動療法の第一歩であり、自己受容につながるきっかけでもあります🌿
「こう感じちゃいけない」と抑え込むのではなく、
「今こんなふうに思ってるんだな」と自分を見守る目を持つこと。
これが、認知行動療法と自己受容の接点なんです。
この先の記事では、
・認知行動療法ってどんな仕組み?
・自己受容との違いと共通点は?
・どうやって日常に活かせばいいの?
といった疑問にじっくり向き合っていきます📖

心が疲れてしまったとき、自分をやさしく扱うためのヒントが詰まっていますので、どうぞリラックスして読んでいって下さいね☺️✨
認知行動療法(CBT)とは?基本構造と考え方
認知行動療法(CBT)って聞くと、なんだか専門的でハードルが高そうに感じるかもしれませんが、
実はとてもシンプルで、「考え方に気づく → 行動に変化を起こす」という実用的なアプローチです☺️
心がつらいとき、「気持ちをなんとかしたい」と思う方が多いですが、実は感情って、勝手に生まれてきて勝手に反応してるんですよね。
認知行動療法では、その「感情が湧き上がる前にある“考え方”のクセ」に注目していきます。
思考・感情・行動の三角形モデル
CBTの基本となるのが「認知(思考)・感情・行動」の三角形モデルです🔺
このモデルでは、
-
思ったこと(思考)
-
感じたこと(感情)
-
取った行動(行動)
の3つはお互いに強く影響しあっていると考えます。
例えばこんな場面をイメージしてみて下さい。
職場で上司に呼ばれたとき、
-
「怒られるんじゃないか…」と考える(思考)
-
ドキドキして不安になる(感情)
-
目を合わせられず、声も小さくなる(行動)
というように、たった一つの「考え」が、その後の感情や行動に大きく波及するんです。
逆に言えば、その考え方に気づくだけでも、感情や行動をやさしく整えていくことができるんですね🕊️
自動思考(Automatic Thought)のメカニズム
CBTでよく出てくるキーワードに「自動思考(automatic thought)」という言葉があります🧠
これは、ある出来事があったときに、自分でも気づかないうちに“パッと浮かぶ思考”のこと。
例えば、
・誰かにLINEを既読スルーされた → 「嫌われたかも…」
・失敗を指摘された → 「私はダメな人間だ」
・休日に予定がない → 「自分は孤独なんだ」
こうした思考って、まるで反射のように頭に浮かんできますよね。
でも、その“反射的な思考”こそが、私たちの感情を揺らしてしまう根っこなんです。
この自動思考に気づかずにいると、
感情の波に巻き込まれたまま、落ち込んだりイライラしたり、動けなくなったりしてしまいます🌀
ネガティブ思考が起きるプロセスを言語化する意味
ここで重要なのが、**「気づく」「書き出す」「言葉にする」**というプロセスです📝
ネガティブな気持ちって、頭の中にモヤモヤっとしたまま漂ってると、どんどん膨らんでいきます。
でも、それをいったん“言葉にして見える化”すると、冷静に観察できるようになるんです。
たとえば、
「私はダメな人間だ」と思ったときに、
「それって、何があったときにそう感じたの?」
「本当に“ダメ”なのか、たまたま“うまくいかなかった”だけじゃないのか?」
こんなふうに、自分の中にもう一人の“ツッコミ役”を持つイメージです👀
言語化することで、感情と距離を取ることができるようになり、
結果的に「自分の思考に流されずにいられる時間」が増えていきます。
これはまさに、自己受容のベースでもある「観察する自分」を育てる練習でもあります🌿

ここまでで、認知行動療法の基礎的な構造──
「思考・感情・行動の関係性」や、「自動思考に気づく重要性」が少し見えてきたと思います。
自己受容とは何か?心理学的な定義と日常での誤解
「自己受容」と聞いて、なんとなく“自分を好きになること”とか“ポジティブになること”って思う方も多いかもしれません☺️
でも実は、自己受容は自己肯定感とは別モノであり、ポジティブさを目指すものでもありません。
むしろ、「今の自分を、そのまま見つめて、否定も肯定もしない」
この“フラットな態度”こそが、心理学で言う自己受容の本質なんです。
ここでは、自己受容という概念について、正しく理解していくために、よくある誤解や混同しやすい言葉と比較しながら整理していきます🧠🌿
自己肯定感との違いを整理する
まず整理しておきたいのが、「自己受容」と「自己肯定感」の違いです📝
自己肯定感は、
「自分には価値がある」「自分が好き」と感じられる心の感覚のこと。
つまり、“評価”がベースになっている概念なんですね。
一方で自己受容は、
**「好きかどうかは別として、今の自分をそのまま認める」**という姿勢。
つまり、“評価しない”ことをベースにしているんです。
たとえば、
・「自分はまだ未熟だな」
・「イライラしやすくて嫌になるな」
そんなふうに思っても、
「でも、これが今の自分なんだよな」と見つめてあげる。
それが自己受容です🕊️
自己肯定感が“高い or 低い”という評価軸にあるのに対し、
自己受容は“そもそもジャッジしない”というスタンスに立っているんですね。
この違いを理解しておくと、「自己受容=ポジティブでいよう」という間違った思い込みから自由になれます✨
「ありのままを認める」は「変わらなくていい」とは違う
ここもよく誤解されやすいポイントです。
自己受容という言葉が広まるなかで、
「ありのままを受け入れるって、何も変わらなくていいって意味でしょ?」
「努力をやめる口実に見える」
と感じる声もSNSなどでよく見かけます。
でも実際には、自己受容は変わることをやめる姿勢ではありません。
むしろ、**「今の自分を否定せずに見つめるからこそ、変わる余地が生まれる」**という感覚に近いです。
たとえば、
「私はすぐイライラしちゃうんだよね」という自分に対して、
「いや、そんなのダメだ」「なんとか我慢しなきゃ」と思うと、
ますますストレスがたまってしまいます。
でもそこで、
「イライラするのは疲れてるからかな」
「自分の中に“ちゃんとしたい”思いがあるんだな」
と受け止めることができたら、不思議と気持ちが落ち着いて、
「じゃあ少し休んでみようかな」と建設的な行動にもつながるんです。
つまり、自己受容は「変わらなくていい」ではなくて、
**「変わる必要があるなら、そこから自然に動けるようになる土台」**とも言えるんですね☺️
自己受容とは「判断せずに観察する力」である
最後に、心理学的な定義をいちばんシンプルに言い換えるなら、
自己受容とは「判断せずに、今の自分を観察する力」です👀
-
いい・悪い
-
強い・弱い
-
成功・失敗
そんな二元的な見方を手放して、
「自分は今こうなんだな」と一歩引いて見つめる姿勢が、まさに自己受容です。
これは感情を抑え込むことではありません。
むしろ、感情をしっかり感じてあげることなんです。
「今日はなんかやる気出ないな」
「また失敗して恥ずかしかったな」
そんな気持ちが出てきたら、
「うん、それが今の自分だね」と言葉をかけるだけでも、
心にふわっと余白が生まれます🌸
自己受容は、目標でも、理想でもありません。

今ここにいる自分と、ちゃんと向き合う“スタートライン”のようなものです。
認知行動療法が自己受容を深める理由
ここまでで、認知行動療法(CBT)の基本的な仕組みと、自己受容の本質が少しずつ見えてきたと思います☺️
じゃあこの2つがどうつながっているのか──つまり、なぜCBTが自己受容を深める助けになるのか?
ここでは、その根拠と実践的な感覚をわかりやすく整理してお伝えします。
結論から言うと、CBTには「自分を責める思考のクセに気づき、それを否定せずに観察する」プロセスが含まれているからです🌿
この“気づいて観察する”というアプローチが、そのまま自己受容の練習にもなっていくんですね。
自分の思考に“気づく”ことが、受け入れる第一歩
CBTのスタート地点はいつも、「今どんなことを考えていた?」という問いから始まります🧠
たとえば、
・友達に既読スルーされた → 「きっと嫌われたに違いない」
・会議で発言を否定された → 「やっぱり自分は無能だ」
こういう“自動思考”に気づくことで、「あ、今わたし、また“嫌われた”って思ってる」と一歩引いた視点を持つことができます。
この「気づく」という行為は、感情を否定することでもなければ、無理やりポジティブに変えることでもありません。
ただ、「そう考えてるな」と知るだけ。
それだけで、不思議と心に少しだけスペースが生まれるんです。
この“気づきの姿勢”が、自己受容の第一歩なんです☺️
なぜなら、気づかないままだと、自分を責めたり否定したりしていることにすら気づけないから。
CBTではこの“気づく”力を育てていく中で、結果的に「ありのままを受け止める力」がついていくんですね。
書く・記録することが感情を客観化する
CBTではよく「思考記録表」や「感情日記」といった書くワークが用いられます📝
これも自己受容とすごく深くつながっているポイントです。
たとえば、
-
出来事:仕事でミスした
-
思考:私は使えない人間だ
-
感情:恥ずかしい、消えたくなった
こんなふうに、自分の考えや感情を書き出すだけでも、
「これは事実じゃなくて“思考”なんだ」と気づけることがあるんです。
紙に書いてみると、モヤモヤした感情が**“言葉として外に出る”**ことで距離が生まれ、
「あ、自分ってこう感じてたんだな」と客観的に見れるようになってきます👀
これはまさに、感情を否定せずにそのまま見つめる自己受容のプロセスそのものなんです。
「書いて整理する」という行為が、「受け止めて、落ち着く」ことにつながっていく。
これが、CBTが単なる思考改善ツールではなく、自分との関係性をやさしくする技術としても使える理由なんですね。
「変える」のではなく「そのまま気づく」のが受容につながる
CBTと聞くと、「考え方をポジティブに書き換える技術」と思われがちなんですが、
本質は**変えることより“そのまま気づくこと”**にあるんです🌱
実際のセッションでも、
「今の自分の気持ちを、変えようとしなくていいから、まず観察してみましょう」
という声かけから始めることが多いんです。
思考を変える前に、「今、どんなふうに感じてるか」「その背景にどんな思考があるか」を丁寧に見ていく。
その上で、「その考え方、今の自分にとって本当に役に立ってるかな?」と問いかける。
この“ジャッジのない問いかけ”の積み重ねが、自己受容の感覚を静かに育てていくんです🕊️
だからこそ、CBTを取り入れることで、
・ネガティブ思考に巻き込まれにくくなる
・自分に対してやさしいまなざしを持てるようになる
・感情に対して「そのままでいい」と言えるようになる

このような変化が少しずつ起こっていくんですね。
SNSや掲示板でよく見る「認知行動療法=修正テクニック」への誤解
認知行動療法(CBT)についてネットで調べてみると、「思考をポジティブに書き換える方法」「マイナス感情をなくすテクニック」といった解説をよく見かけます📱
また、SNSや掲示板では、「ネガティブを無理やり前向きに直すツールでしょ?」といった声もちらほら見かけます。
確かに、CBTには「思考を整理し、行動を変える」という構造はあるのですが、それは単なる“上書き”ではありません。
本質はもっとずっとやさしくて、人の心に寄り添うものなんです🌿
ここでは、そうしたよくある誤解に対して、心理学的な視点から丁寧に答えていきます。
「ポジティブ思考に書き換えるだけ」と誤解されがち
CBTが「ポジティブに言い換える技術」だと思われがちな理由は、
“リフレーミング”という技法が広く紹介されているからかもしれません。
たとえば、
-
「失敗した…」→「成長のチャンスだったかも」
-
「上司に怒られた…」→「指導してもらえたと捉えよう」
こんなふうに、考え方を前向きに変える練習が紹介されることがありますよね📘
でも実際のCBTでは、無理にポジティブに書き換えることは目的ではありません。
むしろ、「そのままの思考に気づき、じっくりと観察する」ことが大切なんです。
「ポジティブに変える前に、まず“なぜそう考えたか”を深掘りする」
このプロセスがないと、自己否定を上から覆いかぶせるような“貼り絆創膏”になってしまいます🩹
「感情を否定して上書きするのでは?」という声への反論
掲示板などでは、
「CBTって感情を無視して“考え方”で乗り越えろって言うんでしょ?」
「ネガティブな感情がダメだって言われてるみたいでしんどい」
といった投稿も見かけます。
その気持ち、よくわかります。
「しんどい気持ち」を抱えているときに、「考え方を変えよう」と言われたら、
「わたしの感情を見てくれてない」って感じてしまいますよね。
でも、CBTが大切にしているのは、
「感情を変える」ではなく「感情を見守る」ことです🧘♀️
むしろ、「今、つらい」「今、しんどい」と感じているその気持ちを、
ちゃんと受け止めた上で、「その奥にどんな思考があるのかな?」と探っていく。
だからこそ、CBTは“感情を否定する”どころか、感情を大切に扱う技術とも言えるんです。
実際には“そのままの気持ち”を肯定するプロセスが重要
認知行動療法を通して大事にされているのは、
**「そのままの気持ちに気づき、それを否定しないで観察する」**というプロセスです🌱
たとえば、
・「何もできなかった自分が情けない」と感じたとき
→ CBTでは「情けないと感じるのはどうして?」と、やさしく問いかけます。
・「また怒ってしまった自分が嫌だ」と落ち込んでいるとき
→ 「怒りにはどんな思いが隠れてる?」と、自分の奥にあるニーズを探していきます。
このとき、
「怒っちゃダメでしょ」
「そんなふうに思っちゃダメ」
という考え方は出てきません。
逆に、
「そう思ったんだね」
「今の気持ち、大事にしてあげよう」
という視点がベースになります🫶
この“そのままの気持ちを認める”姿勢こそ、CBTと自己受容が深くつながっているポイントなんです。
ここまで読んでいただいてわかる通り、CBTは「ポジティブになるための魔法の言葉」ではありません。

それは、「自分の本音にちゃんと向き合いながら、生きやすくなる力を育てる技術」なんです。
書き手の主観|認知行動療法と出会って変わった感情との向き合い方
ここからは少し、僕自身の体験を交えてお話させて下さい☺️

専門的な話だけじゃなく、「実際にどう変わったのか?」を知りたい方も多いと思うので、正直な言葉で綴っていきます。
自分を否定しがちだった過去の思考パターン(自分でも気づいてなかった)
昔の僕は、何かあるたびに自分を責めてました。
ただ、その「責めてる」という自覚すらなかったんです。
たとえば、
・人からLINEの返信が遅れると「嫌われたかも」
・仕事で1つミスがあると「自分は社会不適合者だ」
・朝やる気が出ないと「こんな自分はダメだ」
これ、冷静に見ると「思い込みだよね」ってわかるかもしれません。
でも、当時の自分はそれが“自分の本音”だと思ってたんです。
つまり、自分の中にある「自動思考」に完全に乗っ取られてた状態ですね🌀
感情の波にのまれながら、何がどうなってるのかも見えない。
だからこそ、しんどくなって、何もかも投げ出したくなる──そんな気持ちになることがありました。
書き出すワークで見えてきた「責め癖」の正体
認知行動療法と出会ったのは、「双極性障害」という精神疾患になったときでした。
「思考を記録するだけで、感情が整理されていく」という説明が刺さって、
「とりあえずやってみようかな」って軽い気持ちで始めたんです✍️
最初にやったのは、いわゆる「思考記録表」。
その日に起こった出来事と、それに対する考え・感情を書いていくシンプルなワークです。
何日か続けていくと、驚くことに──
どんな状況でも、結局最後には「自分が悪い」って結論に行き着いてることに気づいたんです😳
・相手の機嫌が悪い → 自分の話し方が悪かった?
・予定が合わなかった → 自分が誘うタイミングをミスった?
・彼女とケンカした → 自分の考え方がおかしいのかも?
こういう“責めグセ”が自分の中に根深く染みついてたんですね。

書き出して「目で見える化」することで、自分でも気づいてなかった思考のクセがくっきり浮かび上がってきました。
「こんな自分でもいていい」と思えるようになった体験
一番大きな転機は、やっぱり5年付き合った彼女との別れでした。
相手は、自己受容を大事にするような価値観の人に惹かれていったと聞いて、
正直、最初は嫉妬とか怒りとか、感情がぐちゃぐちゃで──
「俺の何が悪かったんだよ!」って、ずっと心の中で叫んでました😤
でもふとした瞬間に、「これも、自分を責めてるだけじゃないか」と気づいたんです。
「彼女を責めてるように見えて、本当はずっと“俺がダメだったからこうなった”って言ってたんだな」って。
そこから思考記録をつけるようになって、
怒りや悲しみ、悔しさや惨めさまで、ぜんぶノートに書いていきました📓
最初は汚くて、感情むき出しの文字ばっかりでした。
でも何日か書いていくうちに、ふとこんな言葉が出てきたんです。
「まあ…こんな自分でも、いていいか」
この一言が、自分の中にすーっと入ってきた感覚は今でも覚えてます。
泣けるような解決じゃないけど、「感情に押し流されずに、自分を受け止めることができた」という初めての実感でした🕊️
認知行動療法が教えてくれたのは、
「無理に変わらなくてもいい」
「ただ“気づいて書き出す”だけで、自分との距離が変わる」
という感覚でした。
自己受容って、いきなりできるものじゃないです。

でも、CBTのようなシンプルな技法を通じて、「否定しない」「観察する」って姿勢が少しずつ育っていくんだと思います。
まとめ|自己受容と認知行動療法の関係を知ると心の扱い方が変わる
ここまで読んで下さり、本当にありがとうございます☺️
認知行動療法(CBT)と自己受容、この2つの関係について丁寧に紐解いてきましたが、いかがだったでしょうか?
どちらも専門的な言葉に見えるけれど、実はとても日常的で、誰にとっても“心をやさしく扱うための土台”になるものなんです。
最後にもう一度、この記事の本質を3つのポイントに分けて整理しておきますね📝
自己受容は「変わらないことを許す」力
まず何よりも大切なのは、「今の自分でもいい」と思える感覚です🕊️
それは「成長しなくていい」と言っているわけではなく、
「今すぐ変われなくても、そのままの自分を否定しないでいよう」というスタンス。
認知行動療法を使って「考えを整えよう」とする前に、
まずは「今ここにある気持ち」を否定せずに受け止める。
そこから、本当に意味のある変化が始まります。
つまり、自己受容は**“変わる前に必要な土壌”**なんですね。
思考のクセに気づく=感情の揺れを緩める第一歩
感情はコントロールできなくても、
感情の背後にある“思考のクセ”には気づくことができます👀
認知行動療法のアプローチは、
・何がきっかけでその気持ちが生まれたのか
・そのとき頭にどんな言葉が浮かんでいたのか
こういった内面の流れを整理して、冷静に見つめる力を育ててくれます。
その結果、
「この感情は、今だけのものなんだな」
「いつも“○○しなきゃ”って思ってるな」
と、少しずつ気持ちの波に呑まれにくくなってくるんです。
この“気づき”が、心を整えるための大きな一歩になります☺️
CBTを使って“心の中の自分”とやさしくつながる
認知行動療法は、単に「考えを変えるためのテクニック」ではありません。
本当の意味では、**「自分の心と会話するツール」**なんです🧠🌿
毎日繰り返す感情、思考、行動──
その一つひとつにやさしい目線を向けることで、
「怒ってもいい」
「不安でもいい」
「落ち込んでも、自分を見放さなくていい」
そんな風に、“心の中の自分”と仲直りできる瞬間が増えていきます。
そしてその積み重ねこそが、
「自分と信頼関係を築く」という、何より強くてあたたかい力になってくれるんです。
→ 結論:自己受容とCBTの視点を持てば、感情に振り回されずに“生きやすさ”を手にできる
完璧じゃなくても大丈夫。
不器用なままでも、前に進めます。
大事なのは、気づくこと・見守ること・ゆっくり変わっていくこと。
そしてそのために、CBTと自己受容はあなたの味方になってくれます。
ここまで読んで下さったあなたの心に、少しでもやさしい余白が生まれたなら嬉しいです☺️

ぜひ明日から、感情を“コントロール”しようとするんじゃなくて、“気づいてあげる”ところから始めてみて下さいね🫶✨